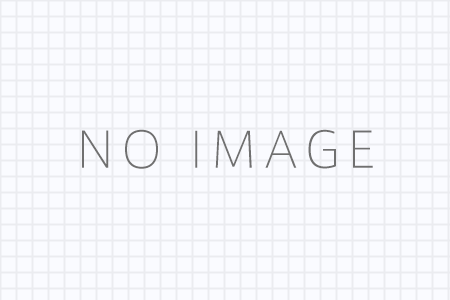こんにちは、亀水です。
今年度、すでに3回ゼミをやりました。
そして、その中で私には少し気になったことがあるのです。
B4のみなさん、起きてますか~~~!!!
B4の皆さんがゼミで誰も発言しないため、ちゃんと話についてきてくれているのかな…と不安になってしまいました。
そこで、毎回のゼミで質問できている私がゼミで質問できるようになる方法を皆さんだけにコソっと教えちゃおうと思います!
そもそも論ですが、(どうして質問なんてしなくちゃいけないのだろう…)って不思議に思いませんか?
という事で、質問のコツを伝授する前に、まずは質問する事の意義についてお伝えします。
質問をする意味について
質問できるようになる技術を伝える前に、質問する事にはどういう意味があるのかについてお話します。(エラそうにすみません)
そもそも、研究とは問いを立てる所から全てが始まります。
- こういう常識がまかり通っているけれど、それって果たして本当なのだろうか?
- この側面から研究した例は多くあるが、別条件で実験してみたらどうなるのだろうか?
このように、世の中の常識を疑い、まだ人類の誰も知らない知見を得に行くのが研究活動なのであります。
研究とは行き当たりばったりの旅みたいなものであり、旅のスタート地点に行くためにはQuestionを打ち立てなくては始まりません。
学部生、それに私も含めた修士の学生は、問いを立てる所を先生にやってもらっているケースが大半ですからあまり実感しないと思いますが、たとえ卒業研究みたいなちっぽけな研究であっても問いがなくては始める事すらままならないのです。
ゼミや学会などの場で質問をするのには、研究をするにあたって最も肝心な”問い”を打ち立てる力を身につける目的があります。
質問すれば質問するほど問う力が身に着くし、たとえB4であっても一年間継続して質問し続ければ独力で研究テーマを思いつくことだってできるかもしれません。
したがって、先生がゼミで
「○○くん、何か質問ある?」
と聞いてきたら、それはピンチどころか研究力を高める大チャンスなのです。
だから、今後は質問の強要を嫌がるのではなく、むしろドンドン積極的に質問に乗り出していって頂きたいと思います。
ゼミで質問できるようになる3つの方法
そうはいっても、そんな簡単に質問できるなら苦労しませんよね?
そこで、以下では、私がゼミで質問魔になるにあたって身につけた3つの考え方についてお話しします。
一時の恥などかき捨てろ!
質問できない最初のケースとして、もしかしたら質問するのが恥ずかしいから質問するのをためらっていらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方に伝えたいのは、そんなちっぽけなプライドなんて捨ててしまえという事ですね。
B4のみなさんが(恥ずかしい…!)と思いながら質問した内容なんて、明日になればほとんどの人の頭からは抜け落ちてしまっているのです。
プライドなど研究力を上げる妨げにしかならないから、そんなものはさっさと拭い去るか鉄鋼所の高炉に投げ込み焼却するべきであります。
また、大学院生が(最上級生にもなってこんな基本的な質問をしていたら後輩にどう思われるだろうか…)と思って質問をためらうケースも稀にありますが、私からすると、上級生だからこそ簡単な質問でもためらわずに手を挙げて欲しいと思います。
上級生が質問をためらうとその雰囲気は必ず後輩に伝播するし、その後輩が質問をためらうとその翌年に入ってくる後輩も基本的な質問をためらうようになってしまいますから。
このように、せっかくしたい質問があるのに質問を躊躇するのはもったいないし悪影響しかもたらさないのです。
基本的な質問は発表者の立場としてもありがたいのですよ。小難しい質問をされるよりはよっぽど答えやすい上に、もし自分の理解があやふやであればその曖昧な点についてハッと気付かされるから。
分からない事を分かるにはある程度の勉強が必要
次に、先ほどのケースとはうって変わり、何が分からないかも分からない場合についてです。
何が分からないかを言語化するには、その分野に関してある程度の知識が必要です。
私は電池の電解液について研究しているから専門分野の話題に多少はついていけますけれども(難しい話は分かりませんけどね)、いきなり数学者に「ねぇねぇ、フェルマーの最終定理についてなんだけど…」と議論を吹っ掛けられても背景知識が全くないので「なんですか、それ…?」ぐらいにしか返答できないでしょう。
このように、ゼミで何が議論されているかすらつかめない場合、その分野に関する知識量が不足している可能性が高いので、まずは図解シリーズや簡単な教科書を読み込んで知識を増やしておくと効果的です。
私の場合、最初期のゼミはまるで外国語を聞いているかのように理解不能でした。
専門用語を全く知らなかったので何を一生懸命議論しているかサッパリでしたし、あまりにも分からなさ過ぎてメモをとるのも諦めかけたぐらいです。
しかし、分からないままでは悔しかったので、図解や教科書を熟読した結果、少なくとも研究室の中での議論の大筋ぐらいはつかめるようになりました。
ちょっとでも勉強し続ければ最低限理解すべき点はイメージできるようになるため、B4の皆さんにはまずはどうかひと踏ん張りして各々の専門分野の概観を掴んでもらいたいのです。(私も勉強の途上なので引き続き勉強し続けます)
どの本を読めば良いか分からなければ、近くの先輩を捕まえて質問してみて下さい。
きっとオススメの参考図書を教えてくれますし、一緒に勉強に付き合ってくれるでしょう。
自分事で聴く&何か質問する前提で発表を聴く
発表を聴く時、もしかしてそれを他人事であるかのように視聴してはいませんか?
もし(どうでもいいや)と内心思いながらゼミに出ていたら、おそらく時間を永遠にドブに捨ててしまうでしょう。
自分にとって有益な時間にしようと思うならば、他人事ではなく自分事で聴かなくてはなりません。
(ちゃんと理解しないとまずい!)といった危機感を持って聞いていれば、少なくとも分からない点に関しては明確に浮かび上がってくるはずです。
また、分からない事が出てきたらその点について質問するという受け身の姿勢ではなく、そもそも何か質問する前提で話を聞くという能動的な姿勢で参加していたら、必ず何か質問をひねり出せます。
私の場合、この姿勢でゼミに出て以来、質問せずに終わった回は一度もありません。
受け身の姿勢だと(どうせ誰かが質問してくれるだろう)と控えめになってしまってゼミ終了が待ち遠しくなるのに対し、攻めの姿勢だと(研究力を高める絶好のチャンスだ!)とアグレッシブに行けるため、質問でのディスカッションも実のあるものになりやすいのです。
どうせ同じ時間を過ごすなら楽しい時間にしたいから、私は今後も質問する前提で話を聞き続ける予定であります。
最後に
ここまで、私が質問できるようになった3つの考え方について紹介してきました。
おさらいすると、
- 一時の恥などかき捨てろ!
- 何が分からないかを分かるには最低限の知識が必要
- 自分事で聴く&質問する前提で聴く
これがこの記事の要点となります。
仮に質問を思いついたとしても手を挙げる勇気が必要となるため、皆の見ている場で質問をする行為はかなりハードルが高いのではないでしょうか(事実、私がそうだったからです)。
しかし、一度勇気を振り絞って質問してしまえばすぐに慣れられるので、最初の障壁(活性化エネルギー)を乗り越えて、どんどん問いを立てる力を身につけて頂きたいと私は思います。
以上です。